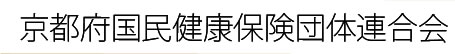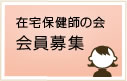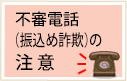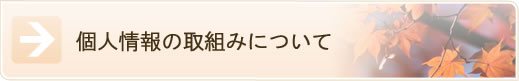
京都府国民健康保険団体連合会個人情報の保護に関する規則
第1条(目的)
この規則は、京都府国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)において、保険者、地方公共団体、福祉事務所、及び社会保険診療報酬支払基金(以下「保険者等」という。)、並びに保険医療機関等から連合会に提供される個人情報、その他連合会が保有する個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び基本的事項を定めることにより、個人の権利利益を保護することを目的とする。
第2条(用語の意義)
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれの当該各号に定めるところによる。
- 個人情報
生存する個人に関する情報であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により特定の個人を識別できるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)をいう。 - 個人情報データベース等
個人情報を含む情報の集合物であって、次に掲げるもの をいう。
(ア)特定の個人情報を電子計算機を用いて検索することができるように体系的に構成したもの。
(イ)電子計算機を用いずに、特定の個人情報を容易に検索することができるように体系的に構成したもの。 - 個人データ
個人情報データベース等を構成する個人情報をいう。 - 保有個人データ
連合会が、開示、内容の訂正、追加又は削除、利用の停止、消去及び第三者への提供の停止を行うことができる権限を有する個人データをいう。なお、保険者等から委託を受けて処理し、管理している診療報酬明細書等は、保有個人データには該当しない。 - 電子計算組織
電子計算機及び関連機器を利用して、定められた一連の処理手順に従って自動的に事務処理を行う組織をいう。 - 診療報酬明細書等
診療報酬明細書、調剤報酬明細書、介護給付費明細書、給付管理票、訪問看護療養費明細書、柔道整復施術療養費支給申請書をいう。 - 医療機関等
保険医療機関、保険薬局、指定訪問看護事業所、介護サービス事業所、介護支援事業所、柔道整復施術所をいう。 - 匿名化
当該個人情報から氏名、生年月日、住所等、個人を識別する情報を取り除くことで、特定の個人を識別できないようにすることをいう。 - オンライン
コンピュータと周辺装置を含む端末装置が通信回線で結ばれ、コンピュータで直接制御されることをいう。 - オンライン請求システム
診療報酬明細書等をオンラインを活用した電子的手法により提出及び受取を行うためのシステムをいう。
第3条(利用目的の特定及び制限)
連合会は、個人情報を取り扱うに当たっては、その利用の目的(以下「利用目的」という。)をできる限り特定しなければならない。又、利用目的を変更する場合には、変更前の利用目的と相当の関連性を有すると合理的に認められる範囲を超えて行ってはならない。
【第2項】
連合会は、あらかじめ本人の同意を得ないで、前項の規定により特定された利用目的の達成に必要な範囲を超えて、個人情報を取り扱ってはならない。又、合併等により事業を継承することに伴い個人情報を取得した場合には、あらかじめ本人の同意を得ないで、承継前における当該個人情報の利用目的の達成に必要な範囲を超えて、当該個人情報を取り扱ってはならない。ただし、次の各号に掲げる場合は、本人の同意を得ずに当該個人情報を取り扱うことができる。この場合、可能な限り匿名化を行うものとする。
- 法令に基づく場合。
- 人の生命、身体又は財産の保護のために必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 公衆衛生の向上又は児童の健全な育成の推進のために特に必要がある場合であって、本人の同意を得ることが困難であるとき。
- 国の機関又は保険者等から委託を受け法令の定める事務を遂行する必要がある場合であって、本人の同意を得ることにより当該事務の遂行に支障を及ぼすおそれがあるとき。
第4条(取得に際しての利用目的の通知等)
連合会は、個人情報を取得した場合は、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかに、その利用目的を本人に通知し、又は公表しなければならない。
【第2項】
連合会は、保険者から委託を受けた業務以外で利用目的を変更した場合は、変更された利用目的について、本人に通知し、又は公表しなければならない。
第5条(利用目的の公表)
連合会は、通常必要と考えられる個人情報の利用目的の範囲を機関誌及びホームページ等に公表するものとする。
第6条(本人の同意及び第三者提供の制限)
連合会は、個人情報の利用目的以外の利用や第三者提供の場合には、第3条第2項各号に該当する場合及び次の各号に掲げる場合を除き本人の同意を得なければならない。
- 保険者等及び他人から委託を受けてその委託業務の達成に必要な範囲において連合会が処理する個人データ。
- 合併その他の事由による事業の継承に伴って連合会に提供された個人データ。
- 連合会が個人データを特定の者との間で共同して利用する場合であって、その旨並びに共同して利用される個人データの項目、共同して利用する者の範囲、利用する者の利用目的及び当該個人データの管理について責任を有する者の氏名又は名称について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときの個人データ。
【第2項】
連合会は、前項第3号に規定する利用する者の利用目的又は個人データの管理について責任を有する者の氏名若しくは名称を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
【第3項】
連合会は、第三者に提供される個人データについて、本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止することとしている場合であって、次に掲げる事項について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置いているときは、前項の規定にかかわらず、当該個人データを第三者に提供することができる。
- 第三者への提供を利用目的とすること。
- 第三者に提供される個人データの項目。
- 第三者への提供の手段又は方法。
- 本人の求めに応じて当該本人が識別される個人データの第三者への提供を停止すること。
【第4項】
連合会は、前項第2号又は第3号に掲げる事項を変更する場合は、変更する内容について、あらかじめ、本人に通知し、又は本人が容易に知り得る状態に置かなければならない。
【第5項】
連合会は、保険者等からの委託業務の実施において保険者等から提供された個人情報について本人に同意を求める必要が生じた場合は、委託元である保険者等が当該本人の同意を求めるものとする。
第7条(適正な取得及び情報の正確性の確保)
連合会は、偽りその他不正の手段により個人情報を取得してはならない。
【第2項】
連合会は、利用目的の達成に必要な範囲内において、個人データを正確かつ最新の内容に保つよう努めなければならない。
【第3項】
第1項及び前項に定めるもののほか、次の各号に掲げる個人情報の取得及び保持をしてはならない。
- 思想、信条及び宗教に関する情報
- 社会的差別の原因となる諸事実に関する情報
第8条(安全管理措置)
連合会は、その取り扱う個人データの漏えい、改ざん、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理のために必要かつ適切な措置を講じなければならない。
【第2項】
前項の目的を達成するため、連合会電子計算機処理データ保護管理規程及び連合会オンライン請求システムに係るデータ保護管理規程等を定めなければならない。
【第3項】
保有する個人情報データベース等の漏えい、改ざん、滅失又はき損等の防止、電子計算機及びそのシステムの盗難、不法侵入、滅失又はき損等の防止、個人情報を含む帳票、書籍、磁気媒体等の保管、搬送、廃棄及び消去時における盗難、漏えい、改ざん、滅失又はき損からの防止、オンライン及びインターネットによる通信回線及び他の電子計算機器との接続による漏えい、改ざん、不法侵入等の防止等のためのデータ保護又は運用管理に関する要綱(マニュアル)等を必要に応じ定めなければならない。
第9条(役職員等の責務及び指導・監督)
連合会の理事、職員、嘱託職員、臨時職員及び派遣職員等、理事長の指揮命令を受けて業務に従事する全ての者(以下「役職員等」という。)は、職務上知り得た個人情報を他人に知らせ又は不当な目的に使用してはならない。又その職を退いた後も同様とする。
【第2項】
連合会は、役職員等に個人情報を取り扱わせるに当たっては、当該個人情報の安全管理が図られるよう、役職員等に対して教育及び研修を行い、必要かつ適切な指導・監督を行わなければならない。
第10条(保護委員会の設置等)
連合会は、個人情報の保護を目的として、連合会個人情報保護委員会(以下「保護委員会」という。)を設置する。
【第2項】
保護委員会は、個人情報を保護するために必要な事項について審査、審議及び調査を行い、その結果を理事長に答申又は報告する。
【第3項】
理事長は、この規則に定めるところにより個人情報が適正に取り扱われているか、その状況について保護委員会に年1回報告するものとする。
【第4項】
保護委員会は、委員9名以内で構成し、その委員は次の各号に掲げる者のうちから理事長が委嘱する。
- 学識経験者 3名
- 保険者代表 3名
- 被保険者代表 3名
【第5項】
委員の任期は、2年とし再選を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
【第6項】
委員は、その職務上知り得た個人情報を他に漏らしてはならない。又その職務を退いた後も同様とする。
【第7項】
保護委員会に委員長、及び副委員長各1名を置き、委員の互選により定める。
【第8項】
委員長は、保護委員会を代表し、会務を総理する。
【第9項】
副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき、又は委員長が欠員になったときは、その職務を代理する。
【第10項】
保護委員会は、委員長の要請により理事長が召集する。
【第11項】
保護委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。
【第12項】
保護委員会の議事は、出席した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
【第13項】
保護委員会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。
【第14項】
委員委嘱後の最初の委員会の運営は、理事長が行う。
【第15項】
保護委員会の庶務は、連合会において処理する。
【第16項】
保護委員会の運営は、この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員長が定める。
第11条(結合の制限)
連合会は、個人情報を処理するにあたって、他の機関及び団体と通信回線による電子計算機組織の結合をする場合は、あらかじめ保護委員会に諮問しなければならない。ただし、法令に基づき結合を必要とする場合は、速やかに保護委員会に報告するものとする。
第12条(委託の制限等)
連合会は、個人情報の取扱の全部又は一部を委託する場合は、法令の定めによる場合を除き、あらかじめ保護委員会に諮問しなければならない。
【第2項】
連合会は、個人情報の処理を委託する場合は、その委託業務の遂行に必要な範囲の情報に限って提供し、委託契約書等において次の各号に掲げる事項について、条件を付さなければならない。
- 個人データの漏えい、改ざん、滅失又はき損の防止その他の個人データの安全管理等個人データの秘密保持の義務に関する事項
- 再委託の禁止に関する事項
- 目的外使用の禁止に関する事項
- 複写及び複製の禁止に関する事項
- 従業者の監督に関する事項
- 事故報告に関する事項、及びそれらに対する連合会の指示に従い改善等適切な措置を講ずる事項
- 提供資料の返還義務に関する事項
- 調査の実施に関する事項
- 前各号に掲げるもののほか、連合会が必要と認める事項
- 前各号に違反した場合における契約解除等の措置及び損害賠償に関する事項
第13条(委託先の監督)
連合会は、個人データの取扱の全部又は一部を委託する場合は、委託された個人データの安全管理が図られるよう、委託を受けた者に対する必要かつ適切な監督を行わなければならない。
第14条(個人データの漏えい等問題が発生した場合の措置及び二次被害の防止)
個人データの漏えい等問題が発生した場合は、早急に事実関係を調査し原因及び問題点を整理・分析し、二次被害の防止、類似事案の発生回避等のため、個人情報の保護に配慮しつつ、可能な限り事実関係を公表するとともに、京都府に速やかに報告するものとする。
第15条(保有個人データの開示)
連合会は、本人から、当該本人が識別される保有個人データの開示(当該本人が識別される保有個人データが存在しないときにその旨を知らせることを含む。以下同じ。)を求められたときは、本人に対し、書面の交付による方法(開示の求めを行った者が同意した方法があるときは、当該方法。)により遅滞なく、当該保有個人データを開示しなければならない。ただし、開示することにより次の各号のいずれかに該当する場合は、その全部又は一部を開示しないことができる。
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合。
- 連合会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼすおそれがある場合。
- 他の法令に違反することとなる場合。
【第2項】
連合会は、前項の規定に基づき求められた保有個人データの全部又は一部について開示しない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
【第3項】
他の法令の規定により、保有個人データの開示について定めがある場合には、当該法令の規定による。
第16条(訂正等又は、利用停止等)
本人から、当該本人が識別される保有個人データの内容が事実でないという理由によって当該保有個人データの内容の訂正、追加又は削除(以下この条において「訂正等」という。)を求められた場合には、その内容の訂正等に関して他の法令の規定により特別の手続きが定められている場合を除き、利用目的の達成に必要な範囲内において、遅滞なく、必要な調査を行い、その結果に基づき、当該保有個人データの内容の訂正等を行わなければならない。
【第2項】
本人から、当該本人が識別される保有個人データが第3条の規定に違反して取り扱われているという理由又は第7条第1項又は第3項の規定に違反して取得されたものであるという理由によって、当該保有個人データの利用の停止又は消去(以下この条において「利用停止等」という。)を求められた場合であって、その求めに理由があることが判明したときは、違反を是正するために必要な限度で、遅滞なく、当該保有個人データの利用停止等を行わなければならない。ただし、利用停止等に多額の費用を要する場合など当該措置を行うことが困難な場合であって、本人の権利利益を保護するため必要なこれに代わるべき措置をとるときは、この限りでない。
【第3項】
第1項の訂正等及び、前項の利用停止等の措置について、次の各号に掲げる場合には、これらの措置を行わないものとする。
- 訂正等又は、利用停止等の求めがあった場合であっても、利用目的から見て訂正等又は、利用停止等が必要ない場合、誤りである指摘が正しくない場合又は、訂正等又は、利用停止等の対象が事実でなく評価に関する情報である場合。
- 利用停止等、第三者への提供の停止の求めがあった場合であっても、手続き違反等の指摘が正しくない場合。
【第4項】
連合会は、前各項の規定に基づき求められた保有個人データの内容の全部若しくは一部について訂正等又は、利用停止等行ったとき又は、訂正等又は、利用停止等を行わない旨の決定をしたときは、本人に対し、遅滞なく、その旨を通知しなければならない。
第17条(開示等手続き)
第15条第1項、第16条第1項及び第2項の規定による求め(以下この条において「開示等の請求」という。)をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した開示等の請求書面(以下「開示等請求書」という。)を理事長に提出しなければならない。この場合、開示等請求書の受付窓口は、総務部総務課とする。
- 氏名及び住所
- 開示等の請求に係る個人情報を特定するために必要な事項
- 前2号に掲げるもののほか、理事長が定める事項
【第2項】
開示等の請求をしようとする者は、理事長に対して、自己が当該開示等の請求に係る個人情報の本人であることを証明するため、理事長が定めるものを提出し又は、提示しなければならない。
【第3項】
次の各号に定める代理人は、開示等の請求をすることができる。この場合、代理人は、開示等請求書に第1項に掲げる事項のほか、代理人の氏名及び住所を記載しなければならない。さらに代理人は、理事長に対して代理人の資格及び代理人本人であることを証明するため、理事長が定めるものを提出し又は提示しなければならない。
- 未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- 開示等の請求をすることにつき本人が委任した代理人
第18条(手数料)
第4条の規定による利用目的の通知又は、第15条第1項の規定による開示を求められたときは、当該措置の実施に関し、手数料を徴収することができる。
第19条(理由の説明)
連合会は、第4条、第15条第2項及び第16条第4項の規定により、本人から求められた措置の全部又は一部について、その措置をとらない旨を通知する場合又はその措置と異なる措置をとる旨を通知する場合は、本人に対し、その理由を説明するよう努めなければならない。
第20条(苦情の処理)
個人情報の取扱に関する苦情の適切かつ迅速な処理に努めなければならない。
【第2項】
前項の措置に関する体制その他必要な事項は、理事長が別に定める。
第21条(保護委員会への報告)
連合会は、第15条の開示、第16条の訂正等又は利用停止等、第19条の理由の説明及び、第20条の苦情の処理を行った場合は、第10条第3項に基づき保護委員会に報告するものとする。
第22条(規則の改正等)
この規則を改正又は廃止する場合は、あらかじめ保護委員会に諮問しなければならない。
第23条(規則違反等の対処・処分等)
連合会は、個人データの漏えい及び改ざんが生じた場合並びに、それらが生じるおそれがある場合には、次の各号に掲げる事項について速やかに適切な対処をしなければならない。
- 担当部課及び委託会社からの状況の報告を受ける等情報収集し、事態の把握及び収拾に努めること。
- 事態の原因並びに問題点を解明し、再発の防止策を策定すること。
- 違反者への連合会職員服務規程に基づく懲戒処分を検討し、公正かつ適正な処分を行うこと。
- 告訴等刑事措置を検討し、重大さに応じて刑事措置をとる。
第24条(委任)
この規則の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。
附 則
- この規則は、平成18年10月1日から施行する。
- 改正前の連合会における個人情報の保護規則第5条により委嘱された保護委員会の委員は、この規則により委嘱されたものとみなす。
- 京都府国民健康保険団体連合会診療(調剤)報酬明細書等の取扱要綱(平成17年4月1日制定)、京都府国民健康保険団体連合会介護給付費請求明細書及び給付管理票の取扱要綱(平成17年4月1日制定)、京都府国民健康保険団体連合会電子帳票データ保護管理要綱(平成18年7月1日制定)、磁気媒体レセプト及び磁気データ等の保管・廃棄に係る取扱要綱(平成17年8月1日制定)、京都府国民健康保険団体連合会事務所管理要綱(平成17年4月1日制定)及び、京都府国民健康保険団体連合会電算室運用管理要綱(平成17年4月1日制定)は、この規則第8条第3項に基づき定めた取扱要綱とみなす。
施行細則
第1条(保有している個人情報)
京都府国民健康保険団体連合会(以下「連合会」という。)が保有している個人情報の主なものは、別表第1(保有している個人情報例)のとおりである。(利用目的・範囲)
第2条(利用目的・範囲)
連合会が通常の業務で想定される個人情報の主な利用目的及び利用範囲は、別表第2(利用目的及び利用範囲例)のとおりである
第3条(公表)
連合会個人情報の保護に関する規則(以下「保護規則」という。)、プライバシーポリシー及び、第1条の保有している個人情報の主なもの(別表第1)並びに、前条の個人情報の主な利用目的及び利用範囲(別表第2)は、機関誌及びホームページへの掲載、又は、パンフレットの配布等で公表しなければならない。
第4条(個人情報取扱窓口)
連合会における個人情報の安全管理計画の立案、開示・訂正・利用停止等、公表、相談・苦情への対応及び受付窓口は、連合会総務部総務課とする。
第5条(匿名化)
個人情報の第三者への通知、共同利用及び研修等で利用する場合には、利用目的を阻害しない範囲で可能な限り匿名化を図らなければならない。
【第2項】
前項の匿名化に当たっては、氏名、生年月日、住所、性別、履歴等を切り取る等削除するか又は、黒色で塗り潰し目視はもちろんのこと透かしても判明しないようにしなければならない。
第6条(研修)
連合会は、個人情報データ内容の正確性・最新性の確保及び、個人情報の保護が確保されるように、そのためのルールの策定並びに、データ管理の技術向上のため役職員の研修を実施しなければならない。
第7条(委託先の監督)
委託先の監督は、毎年委託先から個人情報保護に対する状況報告書を提出させたうえ、所管部長が立ち入り調査を行わなければならない。更に随時又は、必要に応じ委託先が適正かつ正確に個人情報を取扱っているか否か調査・監督しなければならない。
第8条(開示請求の方法等)
開示請求に係る保護規則第17条第1項第3号の理事長が定める事項は、次に掲げるものとする。
- 代理人によって開示請求をしようとする場合における法定代理人又は任意代理人の別。
- 求めようとする開示等の方法。
【第2項】
開示請求に係る保護規則第17条第1項の開示等請求書は、第1号様式(1-1開示用)によるものとする。
【第3項】
連合会は、開示等請求書に形式上の不備があると認めるときは、開示等請求した者に対し、相当の期間を定めて、その補正を求めることができる。この場合連合会は、開示等請求した者に対し、補正の参考となる情報を提供するよう努めるものとする。
第9条(本人等の証明に必要な書類)
保護規則第17条第2項に規定する理事長が定めるものは、運転免許証、旅券その他官公署の発行した資格証書等で理事長が適当と認める書類とする。
【第2項】
保護規則第17条第3項に規定する理事長が定めるものは、次の各号の場合の区分に応じ、当該各号に定める書類とする。
- 法定代理人による場合
戸籍記載事項証明書等及び当該法定代理人にかかる前項の書類。 - 任意代理人による場合
本人の印鑑証明書を添付した委任状及び当該任意代理人にかかる前項の書類。
第10条(開示等の決定期限)
開示等決定は、開示等請求のあった日の翌日から起算して14日以内にしなければならない。ただし、第8条第3項の規定により補正を求めたときは、当該補正に要した日数は、当該期間に算入しない。
【第2項】
連合会は、事務処理上の困難その他正当な理由により前項の期間内に開示等決定をすることができないときは、速やかに、開示等請求した者に対し、その旨及び延長する理由並びに期間を文書により通知しなければならない。
第11条(開示手数料等)
保護規則第18条に規定する手数料の額は、保護規則第15条第1項の規定による開示について2,000円とする。
【第2項】
開示請求をしようとする者は、開示等請求書に前項の手数料の領収書を添付又は、提示しなければならない。ただし、提示の場合は、提示の内容を確認した後写しを撮らなければならない。
【第3項】
開示等請求書において、写しの郵送の方法を希望する者には、開示等書面を極秘・親展、かつ着払い書留郵便扱いで交付しなければならない。
第12条(訂正等請求の方法等)
訂正等請求に係る保護規則第17条第1項第3号の理事長が定める事項は、次に掲げるものとする。
- 代理人によって訂正等請求をしようとする場合における法定代理人又は任意代理人の別。
- 訂正等請求に係る個人情報の内容(個人情報を特定するために必要な事項を含む)。
- 訂正等請求の内容が事実に合致することを証するものの提出又は、提示。
【第2項】
訂正等請求に係る保護規則第17条第1項の開示等請求書は、第1号様式(1-2訂正等用)によるものとする。
第13条(利用停止等請求の方法等)
利用停止等請求に係る保護規則第17条第1項第3号の理事長が定める事項は、次に掲げるものとする。
- 代理人によって利用停止等請求をしようとする場合における法定代理人又は任意代理人の別。
- 利用停止等請求の区分。
- 利用停止等請求の理由(保護規則第3条、第7条第1項及び第3項である事実を証するものの提出又は、提示を要する)及び個人情報の内容(個人情報を特定するために必要な事項を含む)。
【第2項】
利用停止等請求に係る保護規則第17条第1項の開示等請求書は、第1号様式(1-3利用停止等用)によるものとする。
第14条(開示等決定通知書等)
保護規則第15条第2項、及び同第16条第4項の規定による通知は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める通知書により行うものとする。この場合第11条第3項規定の場合を除き、通知書を郵送する場合は普通郵便で、全て極秘・親展扱いとする。
- 個人情報を開示する旨の決定…個人情報開示決定通知書(第2号様式)
- 個人情報を一部開示する旨の決定…個人情報一部開示決定通知書(第3号様式)
- 個人情報を開示しない旨の決定…個人情報不開示決定通知書(第4号様式)
- 個人情報の訂正等をする旨の決定…個人情報訂正等決定通知書(第5号様式)
(一部訂正等の場合を含む) - 個人情報の訂正等をしない旨の決定…個人情報不訂正等決定通知書(第6号様式)
- 個人情報の利用停止等をする旨の決定
(一部訂正等の場合を含む)…個人情報利用停止等決定通知書(第7号様) - 個人情報の利用停止等をしない旨の決定
…個人情報利用不停止等決定通知書(第8号様式)
第15条(開示等請求の拒否)
保護規則第17条第1項の開示等の請求に対し、当該開示等請求に係る個人情報が存在しているか否かを答えるだけで、他人の人権侵害や利益侵害となる場合及び他の法令に違反する場合、並びに国連合会等の業務の適正な執行に著しく支障をきたすおそれがある場合等の個人情報(以下「不開示情報」という。)を開示等することとなるときは、この場合当該個人情報の存否を明らかにしないで、当該開示請求等を拒否するものとする。
第16条(利用目的の通知・公表)
連合会は、保護規則第4条第1項に規定する利用目的の通知及び同条第2項に規定する変更された利用目的の通知については、利用目的並びに利用範囲を書面で通知するものとする。
【第2項】
前項の新たに取得した個人情報及び変更された利用目的が、その後通常の業務で継続して利用する場合には、別表第1及び別表第2を速やかに追加若しくは、変更しなければならない。
第17条(死亡した者の個人の情報)
保護規則上個人情報は、生存する個人情報に限定されているが、連合会の業務の性格から、死亡した個人の情報を保存している場合が多く、この死亡した個人の情報も漏えい、滅失及びき損等の防止のため生存する個人情報と同様に、安全管理に努めなければならない。
【附 則】
この施行細則は、平成18年10月1日から施行する。
別表第1(保有している個人情報例)
- 国民健康保険被保険者情報
- 老人保健受給者情報
- 診療報酬明細書(レセプト)情報
- 柔道整復療養費受給者情報
- 介護給付受給者情報
- 介護給付費明細書情報
- 医療機関、介護サービス機関等の開設者一覧
- 介護保険苦情申し立て者とその関係者の情報
- 高額療養費貸付者一覧
- 交通事故に係る損害賠償請求権行使(第三者求償事務)に関して委任を受けた中の加害者と被害者に関する情報
- 連合会役員及び職員の情報
別表第2(利用目的及び利用範囲例)
- 1、医療保険の審査・支払に必要な利用目的と範囲
- 〔連合会内部での利用に係る事例〕
- ・診療報酬明細書(レセプト)の審査
・保険者等への診療報酬の請求
・医療機関への診療報酬の支払 - 〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
- ・レセプトデータの電算処理のための入力、画像取込み処理の委託
・磁気レセプトの保管委託 - 2、保険者事務の共同処理に必要な利用目的と範囲
- 〔連合会内部での利用に係る事例〕
- ・第三者行為求償事務
- 〔他の事業者への情報提供を伴う事例〕
- ・レセプトの資格確認結果表(兼過誤調整依頼書)及び、給付確認結果表(兼再審査依頼書)の作成委託
・高額療養費給付一覧表(保険者別)、高額療養費支給台帳(被保険者別及び、世帯別)の作成委託
・高額医療費支給台帳(受給者別及び世帯別)の作成委託・医療費通知の作成委託
・被保険者証の作成委託
・退職者医療受給権者リストの作成委託
・第三者求償事務(損保会社等へレセプトのコピー提出) - 3、介護保険の審査・支払・苦情処理に必要な利用目的と範囲
- 〔国保連合会内部での利用に係る事例〕
- ・介護給付費明細書の審査
・介護給付管理票の電算入力(明細書の審査のため)
・受給者等からの苦情処理
・事業者台帳
・受給者台帳
・市町村等への介護報酬の請求
・介護サービス事業所等への介護報酬の支払 - 〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
- ・レセプトの資格確認結果表(兼過誤調整依頼書)及び、給付確認結果表(兼再審査依頼書)の作成委託
- 4、保健事業に必要な利用目的と範囲
- 〔国保連合会内部での利用に係る事例〕
- ・保健事業関連資料の分析(重複受診被保険者一覧表、多受診被保険者一覧表、無受診世帯一覧表、入院患者一覧表、長期入院被保険者一覧表及び、食事療養費減額認定に係る長期入院該当者リスト等)
・医療費分析資料の分析
・糖尿病対策等各種事業推進のための資料作成 - 〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
- ・保健事業関連資料のデータ作成委託(重複、多受診、疾病統計、入院患者関連等)
・医療費分析資料のデータ作成委託 - 5、支援費の支払に必要な利用目的と範囲
- 〔国保連合会内部での利用に係る事例〕
- ・請求書等の審査
・市町村等への支援費の請求
・事業所等への支援費 - 〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
- 6、その他
- 〔連合会内部での利用に係る事例〕
- ・高額療養費支払資金貸付事業の実施
・研修事業の実施
・各種表彰の実施
・会員、理事、監事、事務局の組織並びに補職者名簿、診療報酬等審査委員名簿及び、各種委員会・協議会等名簿の作成・報酬、給与、賃金、手当、旅費等の計算及び、社会保険、労働安全衛生対処並びに、その他昇給・昇格、配置換えへの対処等のため役職員及び臨時要員、審査委員、各種委員名簿又は、記録 - 〔他の事業者等への情報提供を伴う事例〕
- ・総会議案(未調整過誤の医療機関名記載)の印刷の業者委託